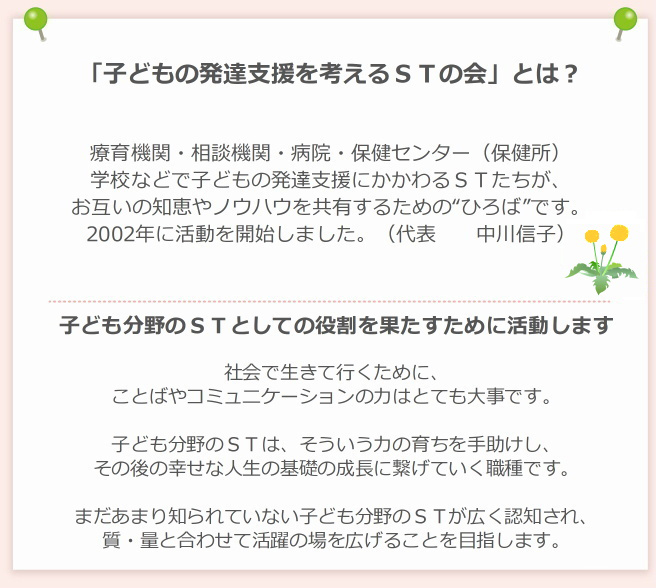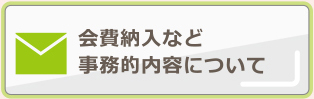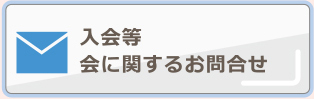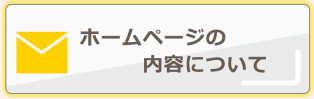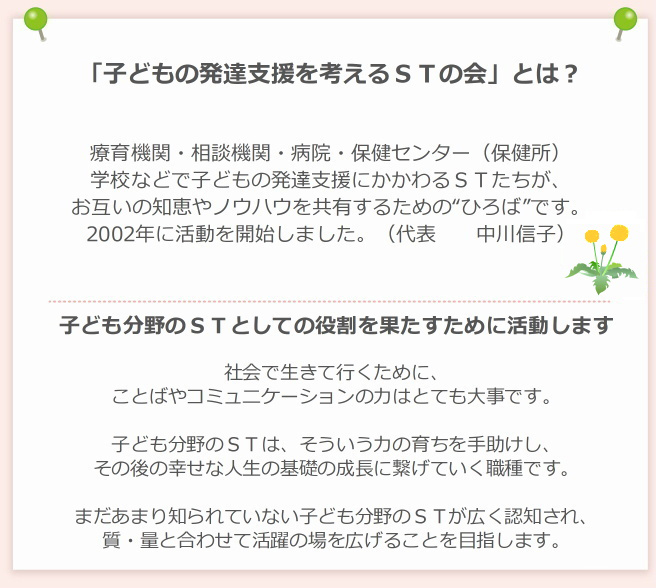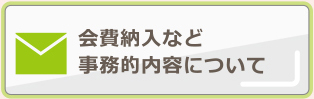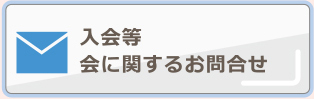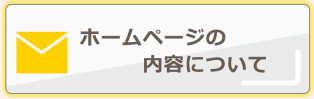「ころころころ どんぐり ころころ いけのなか」
「ちっくんと ちゅうしゃを うっても なかないぞ」
子どもたちに、オノマトペはもちろん、文章のリズムも楽しんでほしい。そんな願いを込めて作ったのが、本書「あいうえオノマトペ」そして、拗音、濁音、半濁音を収録した「あいうえオノマトペ ぱぴぷぺぽいっと」です。
おかげさまで「文字はまだ読めないけれど、文章を覚えて言うようになりました!」「声を出すようになりました!」と、嬉しい報告をたくさんいただいています。先日は「1ページの文字数が少ないので、長い文章を読むのは難しい段階の子どもたちの“音読の導入”として使いやすいです」と、声をかけていただきました。
ところで、本書に使われているオノマトペや感嘆詞などのことば、イラストは、数年前に出版した「ことばを育てるオノマトペカード」「同 ぱぴぷぺぽ編」に収録されているものです。
ことばの出ていない子どもたちと一緒に声を出したい、ことばを体で感じたい、声やジェスチャーで気持ちを伝え合いたい!と、作った絵カードですが、裏面に大きくひらがな1文字が印刷してあることから、小さなお子さんから文字課題に取り組むお子さんまで、楽しく使ってくれています。また、同じカード2セットを使ってカルタ遊びをすると、文字が読めないお子さんだけでなく、おしゃべりが始まっていないお子さんも、声やジェスチャーで読み手側を担当することができ、盛り上がります!
「ころころ」「ちっくん」「ざあざあ」「すいすい」・・・身の回りの音や声、動きやものの状態などを音で表現したオノマトペは、聞き取りやすく真似しやすいこと、意味がイメージしやすいことなどから、私たち言語聴覚士にとって馴染み深い語彙群です。皆さんに使っていただけたら、絵本、カードのオノマトペから、ことばやイメージを広げて遊んだり、子どもたちの声を引き出したりしてくださるのでは・・・と想像し、ワクワクします。
同シリーズ「オノマトペカード 親子のワークブック」は、全ページカラーで、1ページにたくさんのイラストが掲載されています。鉛筆やペンを使った初めてのワークとしてだけでなく、絵本のように眺めて親子のやり取り遊びに使いやすいという声もいただきます。
また、今年、ひらがな文字が少し凹んでいる指なぞり絵本「ゆびでなぞって!ひらがな あいうえオノマトペ」も出版されました。見開き1ページに「あいうえお」「かきくけこ」など一行ずつのオノマトペが配置され、「すいすい そーっと さしすせそ」「なでなで ぬりぬり なにぬねの」などの短い文章が添えてあります。全ページの文章を順番に言うと「あいうえおうた」のように唱えることができます!
カードと絵本は別々の出版社から発行されていますが、どちらのご担当者も、私がSTとして関わったお子さんのお母さんです。子どもたちが繋いでくれたご縁に感謝し、ずっと大切にしていきたいと思っています。皆さんにも使っていただけますように!
2024年8月 子どもの発達支援を考えるSTの会 会員 石上 志保
※表紙画像等については出版社さまより利用許諾を得ております。